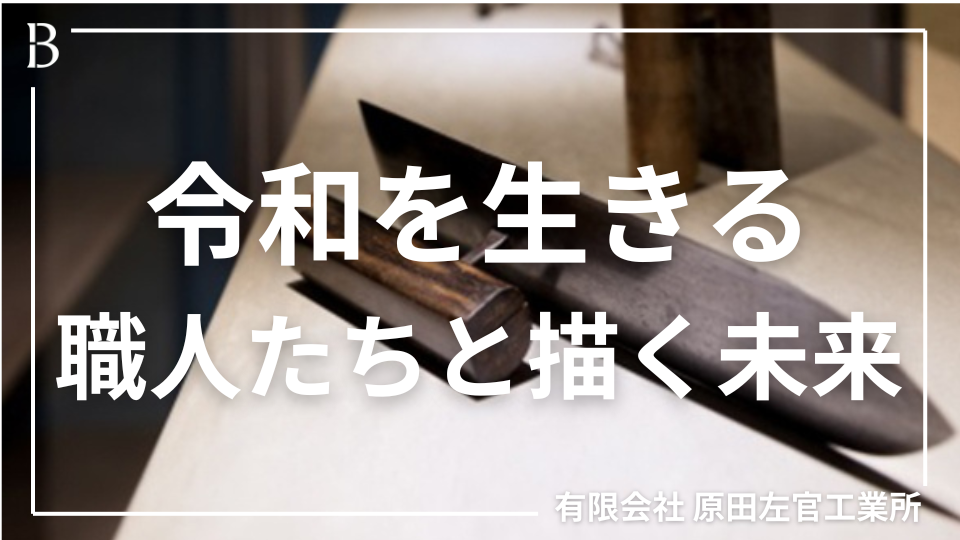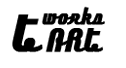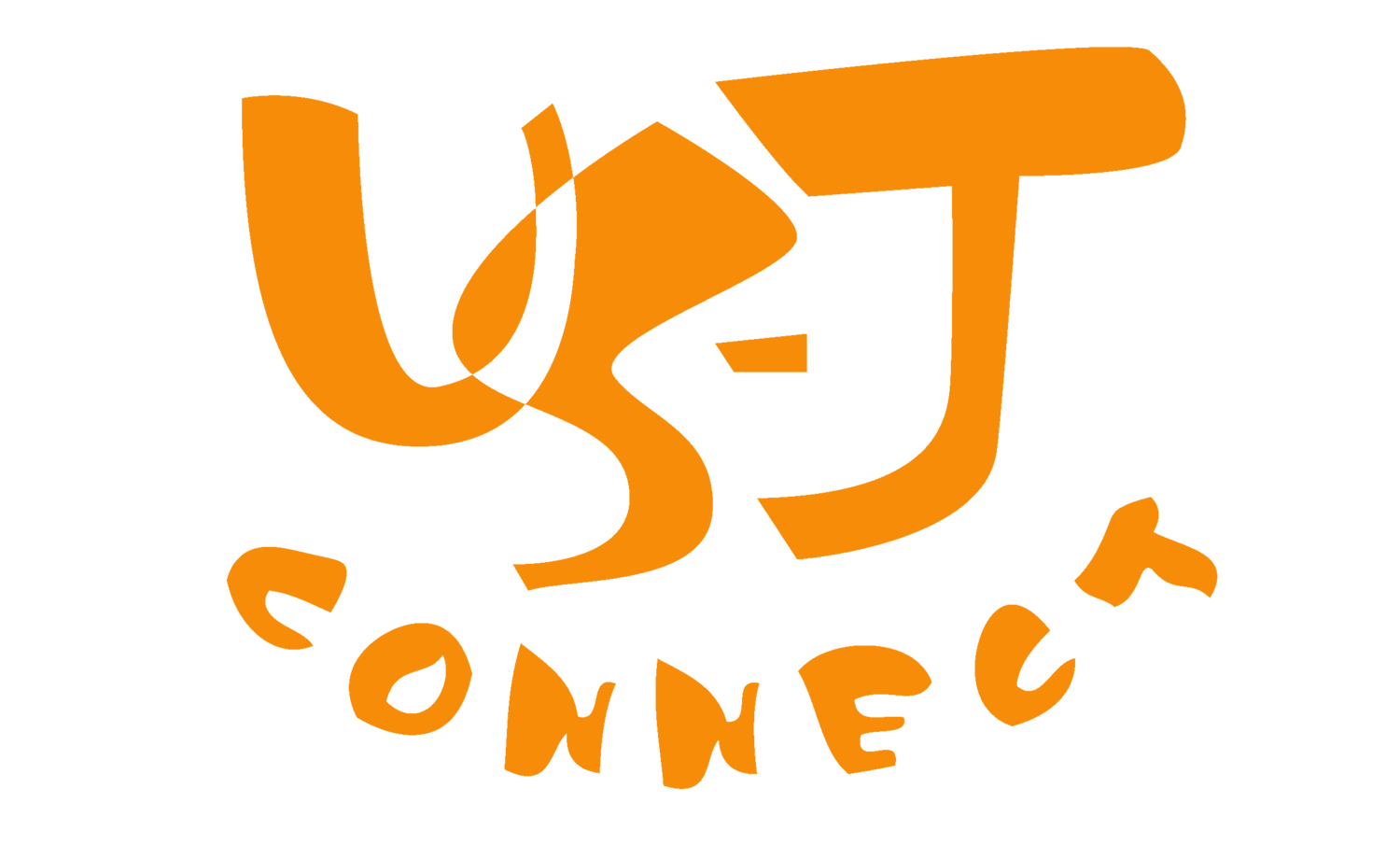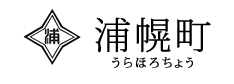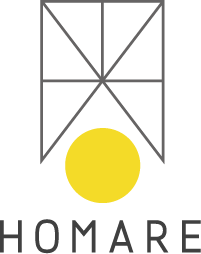夢とロマンを――。東京・文京区にある原田左官工業所では、若い世代の職人たちが活躍しています。平均年齢は35歳。3代目社長の原田宗亮さんは、「互いを高め合いながら挑戦を続けています」と語ります。需要減少や人材不足といった業界の逆風の中、同社はこの10年間で年商を倍増させ、10億円を達成しました。その成長の背景には、原田さんが大切にしている「人への想い」がありました。変わりゆく時代の中で、原田さんはどのように道を切り拓こうとしているのでしょうか。
原田左官工業所の歩み

原田左官工業所は、1949年(昭和24年)に原田辰三さんが創業。1972年(昭和47年)には有限会社として法人化され、2代目の原田宗彦さんが代表取締役社長に就任しました。アイデアマンだった宗彦さんは、業界に先駆けて女性職人の採用・育成を開始し、女性だけの左官チーム「ハラダサカンレディース」を結成。その取り組みは新聞やテレビなど数多くのメディアで取り上げられ、話題となりました。2007年には3代目として原田宗亮さんが社長に就任。「夢とロマン」を創業以来の理念とし、職人たちが夢を持って仕事に取り組み、常に新たな可能性を追求し続けることを信条としています。
職人の在り方を変える/「技術は見て覚えろ」から「互いを高め合う」へ
幼少期から職人たちが身近な存在だった原田さん。学校から帰ると、家には職人たちが集まり、食卓を囲んで食事をしていたといいます。「やんちゃな職人さんが多かったですね」と振り返ります。かつて職人の世界では「技術は見て覚えろ」という風潮が根強く、厳しい修行が当たり前でした。いわゆる「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージもありました。
しかし、時代の変化とともに左官業の需要は減少。住宅の工業化やプレハブ化、建築工法の変化などにより、昔ながらの「塗り」の技術が使われる機会は減少しています。さらに、職人の高齢化が進み、国の調査によりますと、1970年代には全国に約30万人いた左官職人が、2020年には約5万人余りまで減少しました。

「祖父の時代は、生活のために左官をするという感覚でした。しかし今は、『面白さ』がないと担い手は増えません。私たちの会社では、職人同士がアイデアを出し合い、技術を磨きながら成長しています」
アイデアを生み出す職人たちの“修行の場”
原田左官工業所には、職人たちが技術を磨く“修行の場”があります。それが、資材を保管している倉庫です。そこは試作室も併設されていて、様々な材料を用いて試作がすぐに出来るようになっています。ここでは職人たちがアイデアを出し合いながら試作を繰り返し、壁の表現方法を探求しています。「それぞれが自由に提案できる雰囲気が大切」と原田さん。上下関係を尊重しつつも、年齢や経験を問わず教え合う習慣が根付いていることが、多彩な表現方法を生み出す秘訣となっています。
「技術=人」 多様な人材の育成に力を注ぐ
原田さんが特に力を入れているのが「人材育成」です。
「職人全員が名人なわけではありません。野球に例えると、エースで4番だけでなく、8番ライトのような存在も重要です。それぞれに活躍できる場がある。原田左官工業所には、40歳を過ぎて左官職人を目指した人や、IT企業から転職した人もいます。人それぞれの職人としての在り方があり、彼らが集まることで、会社としての強さが生まれています」
職人や社員とのコミュニケーションを大切にし、一人ひとりの魅力を引き出すことを心掛ける原田さん。2012年からは教育方針に「模倣訓練(モデリング)」や動画を活用した学習を取り入れ、新しい技術習得の仕組みを導入しました。「時代に合わせながらも、頑張ろうとする若者を応援し続けたい」と語ります。左官版モデリング訓練とは札幌の中屋敷左官工業が発案したもので、左官業界で広く使われている教育訓練の手法です。
「提案型左官」で多様なニーズに応える
職人たちの「個」を活かしながら、原田左官工業所が打ち出しているのが「提案型左官」です。単に決められた材料や施工方法で仕上げるのではなく、顧客の要望や空間のコンセプトに合わせ、最適なデザインや素材を提案するアプローチです。原田左官工業所は、これまでの「職人が言われた通りに施工する」スタイルを超え、左官職人がクリエイターとして関わる新しい価値を生み出しています。
例えば、ある和食店の壁には、その地域の瓦を砕いて混ぜ、土地の歴史や文化を感じるような空間を演出しました。また、イタリアンレストランでは、イタリアの土を取り寄せ、現地の伝統的な左官技術を取り入れたこともあるそうです。こうした細やかな提案が、店舗ごとに唯一無二の壁を生み出しています。近年では、アートとのコラボレーションが進み、左官の表現の幅はさらに広がりを見せています。原田さんは「左官の技術は、平面的な仕上げだけでなく、立体的な表現にも応用できます。その自由度を活かし、建築の一部をアートとして昇華させることができる」と力を込めます。

さらに、建築業界全体がデジタル技術の進化とともに変化し続ける中、原田さんは「左官の魅力は、手仕事だからこそ生まれる温かみや独特の凹凸感にある」と強調します。3Dプリンターやプレハブ工法が主流になっても、左官の手仕事が生み出す唯一無二の質感は、デジタル技術では再現できない部分が多いと考えています。また、提案型左官のアプローチは海外でも注目されています。特にヨーロッパでは、日本の伝統技術に対する関心が高く、オーダーメイドの左官仕上げが評価されているということです。
「どれだけ技術が進歩しても、手仕事ならではの価値は変わりません。日本の左官技術を世界に広めたい。そのためにも、組織が自立し、私がいなくても続いていく仕組みを作ることが目標です」
伝統を守りながら新たな価値を生み出し続ける原田左官工業所。
その挑戦は、これからも続いていきます。
これからの社会で挑戦する若者たちへ
「自分のできることを考え・知ることで、自分の好みや特性がどんな分野にあるのかを知ってほしい。何事も食わず嫌いをせず、まずは動いてみる、体験してみてほしい。
一回やってみるだけで、自分の可能性が広がるかもしれません。その上で、自分の得意分野になりそうなものを深堀りしてみてほしいです。
どんな分野でも自分の得意分野を伸ばすためにはスキルや資格を取るだけではなく、コミュニケーション能力や想像力を養うことも重要だったりします。
左官業も自分の創造性を出したいのであれば、単なる作業だけではなく、アイデアと対話を大切にしてお客様と作り上げることが出来る仕事です。
だからこそ、可能性を持って進んでいけば、職人の世界は奥深いです。
何かの歯車ではなく、自ら動く、働くということを大切にしてほしいです。」